胡蝶(こちょう)
・チョウの異名
(春の季語)
ごきげんよう。
色、言葉のことを書いたり、
絵を載せている当ブログ。
ふと、
他のことも
書きたくなりました。
そこで今回は、
“蝶の文様”についても
ご紹介します。
まずは言葉から。
夢見鳥
(ゆめみどり)
・チョウの異名
地獄蝶蝶
(じごくちょうちょう)
・クロアゲハの異名
戯れ蝶
(たわれちょう)
・つがいの蝶が仲良く飛んでいる様子
どの言葉も、
優雅でどこか妖しく
不思議な魅力を持っていますね。
油断していると
どこかへ連れて行かれそうな
危うさを感じます。
日本ではかつて
蝶のことを【カハヒラコ】
と呼んでいました。
“川にいるヒラヒラしたもの”
という意味です。
のちに中国語の
“ディエ”という発音から
〈てふ〉と呼ばれました。
“てふてふ”って
音も文字もかわいくていいですね。

ここからは文様のお話。
蝶の文様は
虫の中でも数が多く
平安時代から描かれてきました。
卵から幼虫、蛹、成虫と
姿を変えていく様子から
「立身出世」
蛹から空飛ぶ成虫に変わる姿を
仙人が天に昇る姿に重ねて
「不老不死」
中国語で、蝶(ディエ)と発音が同じ
耋(ディエ)が高齢者を表すことから
「延命長寿」
…などなど、
大変縁起の良い文様なのです。
人気の理由が分かりますね。
古来から人間の魂を表し、
霊的なものと考えられた蝶。
美しくも不気味なその姿は
人を惹きつけてやみません。
✴︎今回の絵のポイント✴︎
“配色”
“黄色い花の中を舞う蝶”
をイメージして描きました。
『夢見鳥』の異名が似合う
女の子の表情も
お気に入りです。
【参考】
エモい古語辞典 堀越英美
「文様」のしきたり 藤依里子
日本異類図典 朝里樹

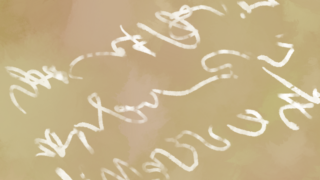



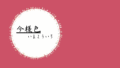
コメント